
フィールドセールスとインサイドセールスの違い:現代営業戦略の最適解を徹底解説
フィールドセールスは対面型、インサイドセールスは内勤型営業手法です。
従来の飛び込み営業から、より効率的かつ専門性の高いアプローチが求められています。
本記事では、フィールドセールスとインサイドセールスの基本的な定義から、それぞれの役割、メリット・デメリット、具体的な業務プロセス、KPI設定、そして両者を効果的に連携させるための戦略まで、現代営業組織に不可欠な分業体制について詳しく解説します。
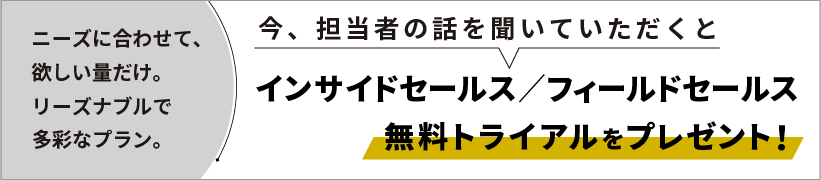
目次
フィールドセールスとインサイドセールスの決定的な違いと連携の重要性
フィールドセールスとインサイドセールスの最も決定的な違いは、「顧客との接点方法」と「営業プロセスの担当フェーズ」にあります。
フィールドセールスは、顧客のオフィスへ直接訪問し、対面での商談を通じて契約獲得を目指す「クロージング」に特化した役割を担います。
これに対しインサイドセールスは、電話、メール、WEB会議システムなどを活用し、非対面で顧客との信頼関係を築き、商談機会を創出する「リードナーチャリング」や「商談設定」が主な役割です。
現代の営業戦略においては、この二つの営業スタイルを独立して運用するのではなく、それぞれの強みを活かすため密接に連携させることが重要です。
インサイドセールスが効率的に見込み顧客を育成し、確度の高い商談機会をフィールドセールスに引き継ぐことで、フィールドセールスは成約可能性の高い顧客に集中でき、営業プロセス全体の効率性と成約率が飛躍的に向上します。
なぜ今、営業分業が求められるのか?それぞれの役割とメリット・デメリット

現代において営業組織がフィールドセールスとインサイドセールスに分業する傾向が強まっているのは、市場環境の変化、顧客の購買行動の多様化、そしてテクノロジーの進化が背景にあります。
この分業体制は、営業活動の効率化と専門性の向上を実現するための重要な戦略的選択となっています。
フィールドセールス(外勤営業)の役割と特徴
フィールドセールスは、顧客の事業所に直接足を運び、対面で商談を行う営業形態です。
その主な役割は、インサイドセールスやマーケティング部門によって育成された見込み顧客に対し、「クロージング」を担うことです。フィールドセールスの主なメリットとして、対面での深い信頼関係構築が挙げられます。
これは、特に高額な商材や長期的な関係が求められるBtoBビジネスにおいて不可欠です。
インサイドセールス(内勤営業)の役割と特徴
インサイドセールスは、オフィス内から電話、メール、WEB会議システムといった非対面チャネルを活用して営業活動を行う形態です。
その主な役割は、見込み顧客の情報を収集・分析し、ナーチャリング(育成)を通じて購買意欲を高めること、そして確度の高い商談機会をフィールドセールスに引き継ぐことです。
インサイドセールスの業務内容は、マーケティング部門が獲得したリード(見込み顧客)に対し、電話やメールでアプローチを開始し、顧客の課題やニーズをヒアリングします。単なるテレアポとは異なり、顧客育成に重点を置く点が特徴です。
インサイドセールスの主なメリットとして、地理的制約がなく、効率的に多くの顧客にアプローチできることが挙げられます。コスト削減に大きく貢献します。
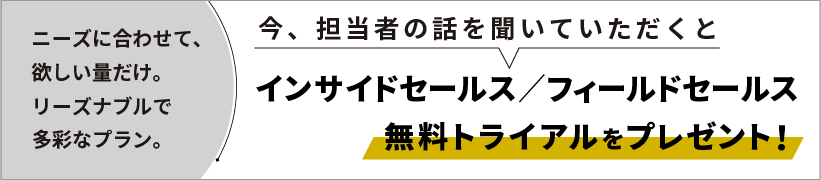
具体的な業務プロセス、KPI、成功事例

フィールドセールスとインサイドセールスが効果的に連携し、営業成果を最大化するためには、それぞれの具体的な業務プロセスを理解し、適切なKPI(重要業績評価指標)を設定することが不可欠です。
フィールドセールスとインサイドセールスそれぞれの詳細な業務フローから、測定すべき指標、そして実践的な連携モデルまで解説します。
フィールドセールスの詳細な業務プロセスとKPI
フィールドセールスは、インサイドセールスから引き継がれた「ホットリード」に対して、最終的な成約を目指します。
その業務プロセスは、まずインサイドセールスからの引き継ぎで、インサイドセールスが獲得した顧客情報(課題、ニーズ、予算、導入時期など)を詳細に共有され、商談の背景を深く理解します。
実際の商談では、顧客を訪問し、製品・サービスの具体的な提案を行います。その後、交渉・条件調整段階で、顧客の予算や要望に応じて調整を行います。
最終的にクロージングで顧客の合意を得て、契約を締結し、受注を獲得します。
契約後のフォローアップでは、成約後も顧客との関係を維持し、カスタマーサクセス部門との連携も重要です。
フィールドセールスの主なKPI(重要業績評価指標)には、成約数、成約率、平均契約単価、商談化率があります。
インサイドセールスの詳細な業務プロセスとKPI
インサイドセールスは、マーケティング部門が獲得したリードを「温め」、商談に値する状態に育成することが主な役割です。
その業務プロセスは、まずマーケティングからのリード受け渡しで、WEBサイトからの問い合わせ、展示会での名刺交換、資料ダウンロードなど、マーケティング活動によって獲得されたリード情報を受け取ります。
次にリードナーチャリング(育成)として、リードに対し、電話、メール、チャットなどを通じて定期的にアプローチし、情報提供や課題ヒアリングを行います。
そして、顧客の興味関心度や購買意欲を段階的に高めるためのコミュニケーションを行います。メルマガやウェビナーも活用します。
ニーズヒアリング・情報提供段階では、顧客の現状、課題、ニーズ、予算、導入時期、意思決定プロセスなどを詳細にヒアリングし、自社製品・サービスがどのように役立つかを説明します。
リードクオリフィケーションを行い確度を見極める重要なプロセスです。
アポイント獲得(商談設定)では、顧客の購買意欲が高まり、具体的な商談に進む準備ができたと判断した場合、フィールドセールスとのアポイントを設定します。
これを「トスアップ」と呼びます。
最後に、フィールドセールスへの情報共有と引き継ぎで、獲得した顧客情報やヒアリング内容を詳細に整理し、フィールドセールスに引き継ぎます。CRMやSFAを活用し、リアルタイムでの情報共有を徹底します。
インサイドセールスの主なKPI(重要業績評価指標)には、アポイント獲得数、商談設定数、リードからの商談化率、架電数/メール送信数があります。
両者の連携モデルと成功事例
フィールドセールスとインサイドセールスの連携は、営業成果を最大化するための鍵となります。
一般的な連携モデルでは、SDR(Sales Development Representative)とBDR(Business Development Representative)の役割分担があります。
SDRは、インバウンドリード(顧客からの問い合わせなど)に対応し、ニーズを深掘りして商談機会を創出します。
BDRは、アウトバウンドリード(企業リストへの架電など)に対して積極的にアプローチし、新規の商談機会を創出します。飛び込み営業とは異なり、データに基づいた戦略的な発掘を行います。
インサイドセールスが収集した顧客情報は、CRM(顧客関係管理)やSFA(営業支援システム)を通じてリアルタイムでフィールドセールスに共有される必要があります。
これにより、フィールドセールスは商談前に顧客の状況を正確に把握し、機会損失を防ぐことができます。
実際の企業における連携による売上向上の成功事例として、あるBtoB SaaS企業では、インサイドセールス部門を新設し、マーケティング部門が獲得したリードの選別・育成、商談設定をインサイドセールスが担当します。
フィールドセールスは、インサイドセールスから引き渡された確度の高いリードにのみ集中する体制を構築しました。
結果として、フィールドセールスの成約率は20%向上し、全体としての売上も前年比150%を達成しました。
この成功は、明確な役割分担と、CRM/SFAを通じた密な情報共有が要因でした。
営業活動を支えるテクノロジーとツール
現代の営業分業体制は、テクノロジーの進化なしには成り立ちません。
CRM(顧客関係管理)とSFA(営業支援システム)の役割が重要です。
CRMは、顧客情報、過去のコミュニケーション履歴、購買履歴などを一元管理し、インサイドセールスとフィールドセールスが共通の顧客情報を参照できるため、連携を円滑にします。
MA(マーケティングオートメーション)との連携では、見込み顧客の行動を自動で追跡・分析し、リードナーチャリングを効率化します。
MAで育成された確度の高いリードは、インサイドセールスに引き渡され、さらなるアプローチへとつながるプロセスを構築します。
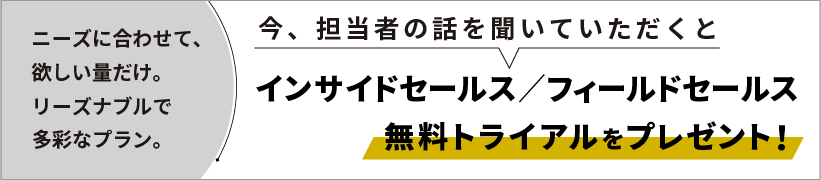
導入・運用のポイントと今後の展望

フィールドセールスとインサイドセールスの分業体制を成功に導くためには、単に組織を分割するだけでは不十分です。
適切な導入戦略と継続的な運用改善、そして将来を見据えた営業スタイルの進化への対応が求められます。
ここでは、インサイドセールス導入時に陥りがちな誤解や課題を回避し、効果的な運用を実現するための実践的なポイントを解説します。
インサイドセールス導入・運用を成功させるためのポイント
インサイドセールスを導入し、効果的に運用するためには、明確な役割分担とKGI/KPIの設定が不可欠です。
フィールドセールスとインサイドセールスのそれぞれの役割、責任者、そして評価指標(KGI/KPI)を明確に定義することで、各担当者が自身のミッションに集中し、連携が円滑になります。
営業とマーケティングの連携強化も重要です。インサイドセールスは、マーケティング部門とフィールドセールス部門の橋渡し役です。
PDCAサイクルによる継続的な改善では、導入後も定期的にKPIを分析し、営業プロセスや連携体制の課題を特定します。
よくある誤解と注意点
インサイドセールスは「テレアポ部隊」ではありません。
単にアポイントを取るだけのテレアポとは異なり、インサイドセールスは顧客の課題を深く理解し、関係性を構築しながら購買意欲を高める「育成」に重点を置きます。
また、フィールドセールスが不要になるわけではありません。
インサイドセールスが普及しても、対面での深い信頼関係構築や、複雑な課題解決、大型案件のクロージングにおいて、フィールドセールスの重要性は変わりません。両者は補完し合う関係であり、どちらかが欠くと全体の効率が低下します。
ハイブリッドセールスの進化
今後の営業活動は、フィールドセールスとインサイドセールスの強みを融合させた「ハイブリッドセールス」へと進化していくと考えられます。
顧客の購買プロセスや商材の特性に応じて、対面と非対面のアプローチを柔軟に組み合わせることで、顧客にとって最も価値のある体験を提供します。
AIやデータ分析の活用により、営業活動はさらに効率化・高度化されるでしょう。ホットなリードを見極める精度が向上し、機会損失を減らすことが可能です。
フィールドセールスとインサイドセールスの連携で実現する営業戦略の未来
本記事では、フィールドセールスとインサイドセールスの違いについて解説しました。
フィールドセールスは対面でのクロージングを得意とする「外勤営業」、インサイドセールスは非対面で効率的にリードを育成し、確度の高い商談機会を創出する「内勤営業」です。
これら二つは互いに補完し合う関係にあり、インサイドセールスが効率的に見込み顧客を育成し、確度の高い商談をフィールドセールスに引き継ぐことで、営業プロセス全体の効率性と成約率が向上します。CRMやSFAといったテクノロジーの活用、そして営業とマーケティングの密な連携が、この分業体制を成功させる鍵となります。
2025年現在、オンラインとオフラインを融合させた「ハイブリッドセールス」が進化し、AIやデータ分析の活用により、より効率的な営業活動が実現されています。
営業戦略の構築や組織改革についてさらに詳しい情報をお求めの方は、ぜひASHIGARUへご相談ください。
専門的なコンサルティングサービスを通じて、貴社の営業課題解決と成長戦略の実現をサポートいたします。
よくある質問
フィールドセールスとインサイドセールスについてよくある質問をまとめました
顧客との接点方法と営業プロセスの担当フェーズに決定的な違いがあります。フィールドセールスは対面、インサイドセールスは非対面で活動します。
顧客の事業所に直接訪問し、対面での商談を通じて契約獲得を目指す「外勤型」の営業形態です。
オフィス内から電話、メール、WEB会議システムなどを活用し、非対面で営業活動を行う「内勤型」の営業形態です。
インサイドセールスによって育成された見込み顧客に対し、対面での商談を通じて最終的な契約獲得(クロージング)を担うことです。
見込み顧客の情報を収集・分析し、育成(ナーチャリング)を通じて購買意欲を高め、確度の高い商談機会を創出してフィールドセールスに引き継ぐことです。
市場環境の変化、顧客の購買行動の多様化、テクノロジーの進化に対応し、営業活動の効率化と専門性の向上を実現するためです。
顧客と対面することで深い信頼関係を構築でき、特に高額な商材や長期的な関係が必要なBtoBビジネスにおいて不可欠です。
地理的制約がなく、効率的に多くの顧客にアプローチできるため、営業コストの削減に大きく貢献します。
いいえ、異なります。
インサイドセールスは単にアポイントを取るだけでなく、顧客の課題を深く理解し、関係性を構築しながら購買意欲を高める「育成」に重点を置きます。
CRM(顧客関係管理)やSFA(営業支援システム)が、顧客情報の一元管理とリアルタイムでの情報共有を可能にし、連携を円滑にするために重要です。








